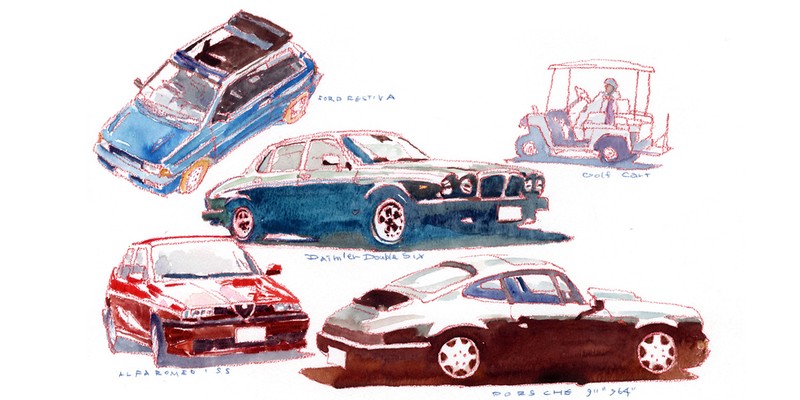2017.06.13
猿が騒ぐと雨が降る?雨の前に起こる不思議なこと
かつて、日本には雨の兆しを告げる多くの言い伝えがあった。今や天気予報を見れば数日先の天気まで把握できてしまうが、昔の日本人は熊や猿などの動物、あるいは風や雲の様子から雨を予期していた。生活のために誕生した、雨の到来を知らせる数々の言い伝えは、そんな当時の背景をも伝える「物語」として今に残る。
- CREDIT :
文/畑中 章宏(作家・民俗学者)
甚左が渥美半島の亀崎港で、三河に向かう船を待っているとき、こんな場面を見聞きした。信州から来た薬商人と、三河へ灸をすえてもらいにいく百姓が、沖のほうを向いて、虹の話をしていた。
「薬商人は晩の虹は雨がふるしるしだといいました。百姓は晩虹は晴れるしるしだといいました。」
虹と天気の相関でいえば、「朝虹は雨、夕虹は晴れ」だという地方が多いが、信州の薬売りは「晩の虹は降雨の徴候だ」と主張したのである。
降雨をめぐるこうした言い伝えが日本には他にもたくさんある。その背景には、日本に水田農耕を生業にする者が多かったことがある。

身近な動物の動作をめぐっても、ネコが顔を洗ったり、ツバメが低く飛ぶと雨になるなどといわれてきた。どちらとも、湿度の増加と関連がある指摘するむきがある。
熊を殺すと雨が降る?
タイトルになっている「熊を殺すと雨が降る」は狩猟集団「マタギ」の口伝(くでん)で、山の神が清らかな山を汚したことに怒り、雨や雪を降らせて、血を洗い流しているのだという。“科学的”には、熊は天気が崩れる前に多量に餌を取る習性があり、このときに撃たれることが多いからだと説明される。
山の民の同様の言い伝えに、「山で猿が騒ぐと、明日は雨降りになる」というのもある。こちらのほうも、猿は雨に濡れるのを極端に嫌うこと習性にもとづくらしい。雨が何日も降り続くと猿は巣にこもり、餌が採れずに痩せ細ってしまう。そこで「猿撃ちは雨降り前、雨上がりの猿は撃つな」といわれる。
豪雨の前に聞こえる川の話し声
井堀(いぼり)という村で大雨が降り続き、木曾川が増水して、村人たちが水番をしていた。そんなある夜のこと、対岸の淵からしきりに、「やろうか、やろうか」としきりに呼ぶ声がする。村人たちは気味悪く思うばかりで、どうすることもできずに顔を見合わせていた。しかしその声がいつまでも止まないので、人夫の一人が「よこさば、よこせ」と返事をしたところ、流れは急に増し、大水が押し寄せて、一帯の低地を海のようにしてしまった――。
「やろうか、やろうか」という不思議な声は、上流で発生した土石流の轟音が、下流にまで聞こえてきたものではないかと説明される。
現代の私たちは、雨具の準備を怠らないため、天気予報を気にするぐらいのものである。こうした雨情を愛でる習俗は都市文化が広まった近世にもあった。それは、生活の糧を得るため、天災から逃れるために、雨の予兆にじゅうぶんな注意を払い、豊かな口承文化を受けついできたのである。
これから先は、人間生活の利便のために創造された人工知能や人工生命たちが、雨にまつわる新しい口伝を生み出していくかもしれない。
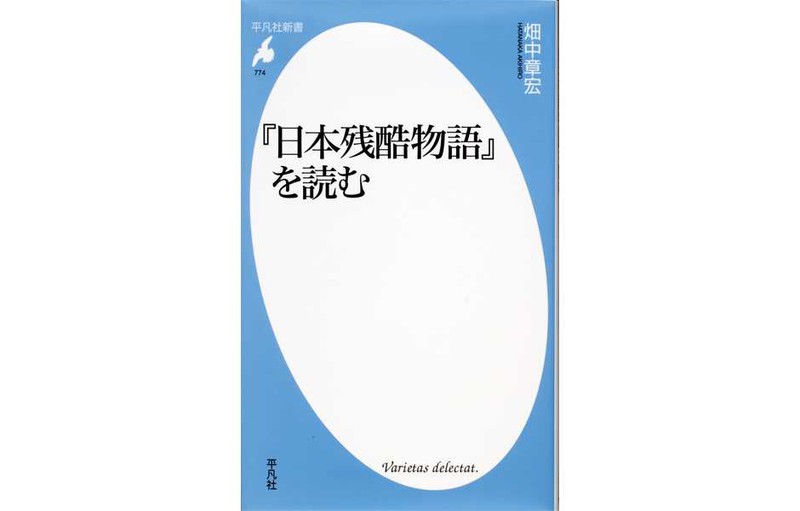
● 畑中章宏 / 作家・民俗学者
1962年生まれ。日本人の民間信仰や民衆史をとおして、現代社会を考える活動を展開。著書に『柳田国男と今和次郎』『『日本残酷物語』を読む』(平凡社)、『災害と妖怪』『津波と観音』(亜紀書房)、『ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか』『蚕』(晶文社)、『天災と日本人』(筑摩書房)ほか。