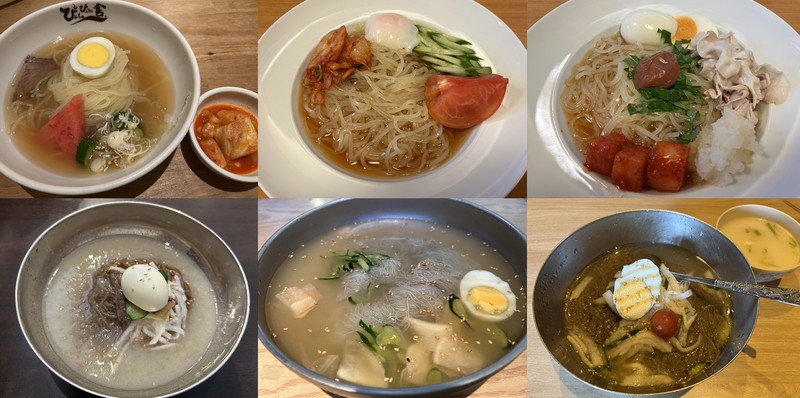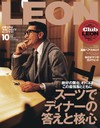2022.04.16
スマホでは聴けない“高音質大音量”は映画館で聴く!
もっともメジャーな音楽プレイヤーとなったスマホは、ほとんどの場合、圧縮音源。そんな、CDよりも劣化した音質に慣れ親しんだことが、「“高音質大音量”を映画館で満喫したい」という潜在需要に。今、『コーダ あいのうた』などの音楽系映画がブームです。
- CREDIT :
文/スージー鈴木(評論家)
音楽の魅力を増幅したのは、映画館(筆者はシネコンで観た)の高音質大音量の音響装置だ。そもそも『コーダ』はApple TV+によって配給される配信系の作品なのだが、日本国内では映画館で観られたのがラッキーだと思った。

私は日本語吹替版を観たのだが、ポーシャというわがまま娘の声優を担当したアイナ・ジ・エンドの歌が抜群で、字幕版ではなく吹替版を観てよかったと思ったものだ。
2作に共通するのは「音楽(系)映画」ということ。これら以外にも、今年に入って『ウエスト・サイド・ストーリー』やビートルズ『ゲット・バック』の劇場版が盛り上がり、昨年は『アメイジング・グレイス/アレサ・フランクリン』や『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』などが話題を呼んだ。
私はこれらの「音楽映画」、つまり「聴く映画」のブームの背景に、「“高音質大音量”を映画館で満喫したい!」という潜在需要の存在があると考えている。今回は、そのあたりを具体的に説明していきたい。
スマホの普及で変わったこと
現代は、大げさに言えば「史上もっとも長い時間、人々がイヤホンを着けている時代」を迎えている。ウォークマンによって80年代前半に伸長した「イヤホン(ヘッドホン)着用時間」は、スマートフォンの普及で、さらに大きく伸長した。
ポイントは、スマホで聴かれている音源は、ほとんどの場合、圧縮音源だということだ。つまり、われわれが日がな一日聴いているあの音は、CDよりも劣化した音質なのである。具体的には「MP3」や「AAC」などの形式で、データサイズが原音の10分の1ほどになる分、音質も劣化する。
だが、正直に白状すれば私は、サブスクを使ってスマホで音楽を聴いているとき、CDに比べて音質が劣化しているとは、ほとんど感じない。耳が鈍感なこともあろうが、データサイズの減少分ほどには音質劣化しない技術が使われているのだろう。
だから、『シング』のサントラCDも買ったはいいが、いちいちCDデッキのトレイに載せて聴くのが面倒なので、アイナ・ジ・エンドの歌をサブスクで聴きながら、CD封入の歌詞カードを読むという、ちょっと倒錯した楽しみ方になっているのだが。
しかしかつて、自らが登壇するカルチャーセンターの講座で、iTunesでダウンロードした音源(M4A形式)を、スピーカーを通して大音量で聴いてみたとき、音質の劣化を痛感した。具体的には、音がサビついているような感じがした。「ずっと気にならなかったけれど、実はこんな音を毎日聴いていたのか」と驚いたのだ。
思うのは、圧縮音源に人々が慣れすぎた結果、「高音質大音量」への需要が、無意識のうちに蓄積されているのではないかということである。ただ、この需要に関しては「ロスレス」「ハイレゾ」による高音質サブスクが、今後は代替していくのかもしれないが。
もっともメジャーな音楽プレイヤーはスマホ
言うまでもなくスマホにおいて、音楽プレイヤー機能は、機能全体の中のワン・オブ・ゼムに過ぎない。人によって異なるだろうが、一般的にはウェブブラウザ機能や、SNS機能のほうが、より多く長く起動しているだろう。
結果「ながら聴き」になってしまう。スマホで音楽を聴きながら、他のアプリに注意が分散したり、またスマホは小型軽量なので、聴きながら移動したり、あるときには聴きながら寝てしまったりと、別の行動をしながらの「ながら聴き」になる確率が高い。
言い換えれば、今やもっともメジャーな音楽プレイヤーであるスマホは、「音楽そのものにもっとも没入しにくいプレイヤー」なのだ。
対して映画館は、強制的にスマホから隔絶され、音楽と映像に完全没入できる。後に触れるコロナ禍の影響もあって、今や、唯一の「音楽没入空間」だと言えよう。
そして、「高音質大音量」需要に向けて、これが最大の要因だと思うのが「スピーカーで音楽を聴く機会の減少」である。
「スピーカーのない生活」となった現代
そんな状況を補完するために、私なども、Bluetoothスピーカーをスマホとつないで使ったりしているが、聴こえてくる音は、もともと圧縮音源であり、また、大音量で聴ける住宅環境もない。
かつて、昭和の時代にFM雑誌(というのがありました)で見た「リスニングルーム拝見」のようなコーナー。オーディオマニアの読者が、凝りに凝ったシステムコンポや自作のスピーカーを自慢する企画——私(たち)は、あのような部屋に、どうやら一生縁がなさそうな感じだ。
「スピーカーのない生活」を言い換えると、「スピーカーから空気を震わせて、ハイファイな高音・低音を耳に流し込む、あの快感から無縁な生活」である。
私事になるが先日、ゴダイゴのミッキー吉野氏と、ゴダイゴのLP『OUR DECADE』を爆音で聴くイベントを開催したのだが(3月22日、於:南青山Baroom)、異常に感動的だった。正直、ちょっと目頭が熱くなったりもした。
「あぁ、やっぱり音楽は、空気を震わせて聴くものだ」と痛感した。イヤホンでチマチマ聴くのが音楽じゃない、とまでは言わないが、それだけが音楽じゃないとは断言できる。
以上、長々と書いた「圧縮音源の常態化」「スマホによる“ながら聴き”」「スピーカーのない生活」に加えて、追い打ちをかけたのが、言うまでもなくコロナ禍だ。
ライブやイベント、カラオケなど、高音質や大音量に生で触れる機会が一気に喪失されたこと。これらが相まって、映画館という「高音質大音量」空間で「聴く映画」に没入する背景が生まれてきたと考えるのである。
「リスニング空間」としての潜在マーケット
そして、そんな需要の受け皿として、特に映画館には大きなチャンスがある。具体的には、「聴く映画」から転じて、映画以外、つまり映像なしの「リスニング空間」としての潜在マーケットだ。
例えば、シネコンの巨大スピーカーを使って、名盤レコードを「高音質大音量」で聴くイベント(かつて「レコード・コンサート」と呼ばれたもの)。この企画、内容もシンプルだし、またそれほどの元手も要らない。ちょっとしたレコードプレイヤーとLPがあればいい。
大滝詠一『A LONG VACATION』を、A・ B面通して、爆音で聴くイベントがあるとして、それが映画と同程度の料金であれば、私はぜひ参加したいと思う。
映画『コーダ あいのうた』を盛り上げるのは、ジョニ・ミッチェルの『Both Sides Now』(青春の光と影)という曲だ。「高音質大音量」に包まれて、映画館でうっとりとしながら私は、映像に加えて音という両面(Both Sides)の潜在マーケットについて考えていた。