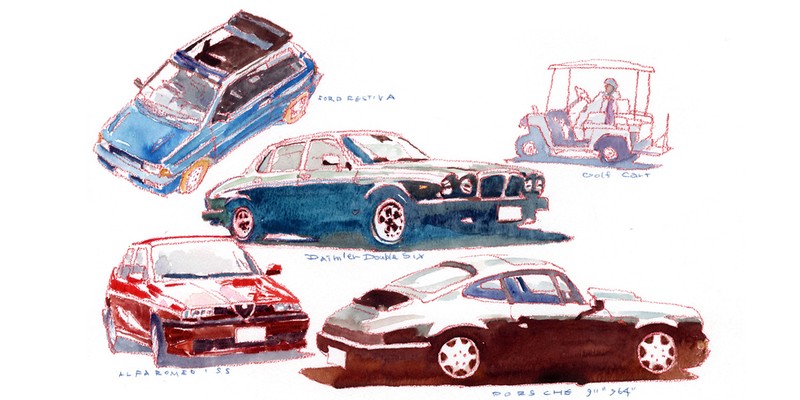2019.04.04
それでも結婚したいなら、それでも結婚を続けたいなら。結婚の未来とは?
晩婚化が進み、生涯未婚率も高まり、さらには結婚したカップルの3組に1組が離婚するという現代。結婚という制度に明日はあるのか? 中央大学の山田昌弘教授にお話を伺いました。
- CREDIT :
文/伊野上真凛

さらにマスコミには日々不倫を糾弾するニュースがあふれ、結婚したカップルの3組に1組が離婚するという現実。一方ではそれでも、結婚を求めて必死に婚活を繰り返す人々がいます。今の時代、結婚という制度は大きな問題を抱えているように思えます。
LEON読者の多くはすでに既婚者かもしれませんが、男にとって結婚が女性との理想的な関係の礎にならないとすれば、それはまた由々しき問題でもあると思うのです。ではなぜ、結婚という制度は機能不全に陥ってしまったのか? そして、これを再びうまく機能させるためには何が必要なのか? その答えを求めて「パラサイト・シングル」「格差社会」「婚活」といった数々のパワーワードを生んできた、社会学者で中央大学文学部の山田昌弘教授にお話を伺ってみました。
見合い結婚は経済的な契約だった
「その昔は複数の女性の世話をしている男性はむしろ偉い、甲斐性があると評価の対象にさえなっていたのです。公的な立場にある政治家や官僚でも、妾や愛人をもち、不倫をしている人は珍しくなかったわけです」と山田教授。
ところが戦後、女性の地位が向上し「自由恋愛」が盛んになり、「恋愛結婚」が主流になると、妾や愛人、不倫などは恥ずべき裏切り行為と認識されるようになります。
「とりわけ今の日本は嫉妬社会。不倫は家庭という経済生活を壊すものでもあり、大きな非難の対象となるのです」(山田教授・以下同)
しかし、そもそも恋愛=好き嫌いの感情はそう長続きしないというのが定説。人類学者のヘレン・フィッシャー博士によれば恋愛感情が続くのは4年が限界とか。そこに重きを置きすぎる関係が破綻を招くのは、ある意味必然とも言えるのです。

現代の若者は恋愛と結婚を別物と考える人が多い
「現代の若者が結婚に求めるものは、愛情よりも安定した経済生活なのです。そこで選ぶべき結婚相手は、愛する人よりも、学歴がよくて収入のある人物ということになります。恋愛する若い男女が減っているのは、恋愛と結婚は別物と考える人が多いからでしょう。学生に話を聞いてみると、一時の感情で結婚するのはよくないと話しています」
それはある意味冷静な判断かもしれません。しかし、ここにも問題があります。長らく続く景気の低迷が雇用格差の拡大を産み、経済的な契約である結婚にも格差が生じているのです。
「正社員での就職率は大きく減少し、半数が派遣社員やパートなどの非正規雇用就労を余儀なくされています。若者の間で広がる収入格差は、恋愛や結婚にも大きな影を落しているのです。格差の拡大により非正規雇用者が増えたことで、女性が結婚相手として選びたい男性の数自体が大幅に減少してしまいました。それでも、子供を育てて豊かな家庭を築きたいと願う女性たちの気持ちは変わりません。みんな子供を産みたがっているし、家庭で育てたいと願っています」
山田教授によれば、こうした状況の中で“婚活”が生まれたのだそう。“婚活”は、2008年に山田教授が著した「『婚活』時代」に登場して一気に世間に認知されるようになった言葉です。著書では、意識的に結婚相手を探さなければ結婚できない時代になったことが記されています。
日本人は世間体や見栄にとらわれている民族
「元々日本人は非常に世間体や見栄にとらわれている民族です。自分の意思よりも、周囲からどう評価されるかに重きをおくのです。特に日本人女性はこの傾向が強く、結婚相手には姉妹や親戚、友人に紹介しても恥ずかしくない学歴や収入の相手を選ぼうとします。基準は、自分の父親や自分自身より上であること。ところが今は女性の学歴も高くなって、社会進出も進んでいますので、この面でも男性のハードルは上がる一方になってしまいました」
結果、女性たちは理想の男性と巡り会うことが難しくなり、結婚そのものが減少する原因になっていると言います。
そしてこのような状況が続けば、今までのように男性が女性を生涯にわたって養う形の結婚関係はますます難しくなります。山田教授は「女性たちが結婚に憧れる気持ちがある限り、結婚という制度が不要になることはない」としつつも、その結婚は今とは違うスタイルにならざるを得ないだろうと言います。ではそれは、どんな形なのでしょう?

男女とも従来型の結婚観を変える必要がある
ところが日本では状況が違います。
「多くの女性は今もって自ら働くよりも、経済力のある男性に養ってもらったほうが楽であり、リスクを背負わずに済むと思っています。加えて、現在も既婚者女性の大半がパート勤務であり、女性の収入は上がっていないのが実情です」
この状況を踏まえると、日本がすぐにフランスのようになることはなさそうです。とはいえ、今のままでは何も解決しないことも事実。ではどうするべきか。山田教授は男性も女性も根本的に変わるしかないと言います。
「まず、男女とも結婚に対する考えをもっと柔軟にすること。そして、女性は経済的に男性に依存する、という従来型の結婚観を変えることが必要です。男性も経済力以外にコミュニケーション力を身につけるなど、今まで以上に自分を磨くことが必要になるでしょう」
そのような意識変革の先にしか、新しい結婚のカタチは見えてこないと山田教授。
「今後は恋愛と結婚の分離がますます進んでいくでしょう。今はインターネットによる『お見合い』サービスなども盛んですが、結婚は結婚として、恋愛のように相手に過度に期待することなく穏やかにやっていく、という方向もあると思います」
お互いに期待しすぎない穏やかな関係。それはフランス人が実践する男女の関係とはまた違うものになりそうな気もします。願わくば、より細やかな感情のやりとりを重んじる日本人ならではのものとなって欲しいものです。もしかすると前述の恋愛と結婚を別物と考える若者たちは、そんな新しい男女の関係づくりへの第一歩を、すでに踏み出しているのかもしれません。
● 山田昌弘
1957年東京都生まれ。1981年東京大学文学部卒。現在、中央大学文学部教授。専門は家族社会学。学卒後も両親宅に同居し独身生活を続ける若者を「パラサイト・シングル」と呼び、「格差社会」という言葉を世に浸透させたことでも知られる。また、「婚活」という言葉を世に出し、婚活ブームの火付け役ともなった。主な著書に『「婚活」時代』(ディスカヴァー携書)、『モテる構造―男と女の社会学』(ちくま新書)ほか。5月に新刊『結婚不要社会』(朝日新書)発行の予定。