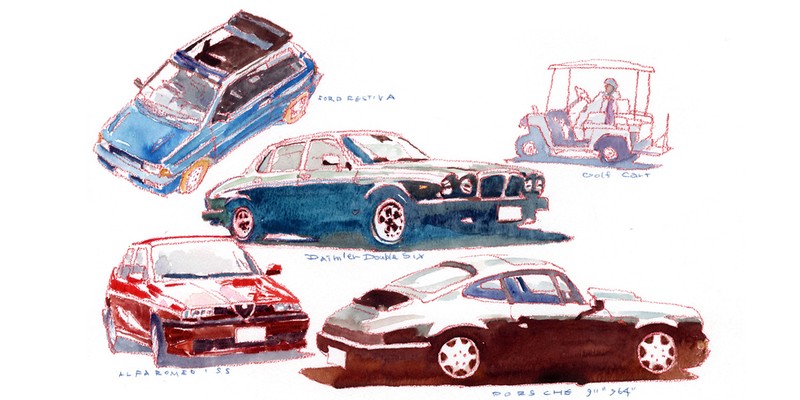2020.10.24
太田光「M-1審査員の依頼があっても断るワケ」
爆笑問題・太田光氏の書籍『違和感』には、「ウィズコロナ」の新しい日常を考えていくヒントが満載! 「漫才が天職」とは思っていないという太田氏の、才能と技術、才能と努力に関するメッセージとは?

「売れる」芸人を見極められるのか
じゃあなぜ、才能について語るのが難しいのかと考えると、結局、わからないからだと思う。才能を「売れる」という言葉に置き換えてみてもそうで、この世界は、誰がいつ売れるかだなんて誰にもわからない。
ピコ太郎がいい例だ。『ボキャブラ天国』という番組で一緒にやっていた頃は、底ぬけAIR-LINEというお笑いトリオだったんだけど、その後、古坂大魔王の名でピン芸人として活動していく。そんな古坂を、くりぃむしちゅーの上田や俺は「あいつが売れないなんておかしい」とずっと言い続けていた。でも、売れない。どこに行ってもなにをやっても売れやしない。
そんな古坂大魔王を見かねて、どうにかしたいと思った上田は、さんまさんに売り込みまでする。ところがその時に「古坂という日本一おもしろいやつがいるんですよ」と言っちゃったもんだから、さんまさんが「日本一」という言葉に食いついちゃう。
「俺よりおもろいんか?」と言われた上田は「あ、違います。日本2位です」と慌てて訂正したっていうね(笑)。そんな感じで苦労していた古坂大魔王なのに、ジャスティン・ビーバーが、ひとことつぶやいただけで大ブレイクしたのだから、この世界の売れる・売れないは本当にわからない。
小島よしおが売れた時もそうだった。うちの事務所は『タイタンライブ』というお笑いライブを2カ月に1回やっているんだけど、その舞台には、日本エレキテル連合などのタイタン所属のメンバー以外に他事務所の芸人にも出演してもらっている。
他事務所で若手芸人の場合は、わざわざネタ見せに来てくれて、うちの作家や『タモリ倶楽部』などの放送作家である高橋洋二さんが「おもしろい!」と感じたら出演してもらうんだけど、ある時、ブレイク前の小島よしおがネタ見せに来てくれたことがあった。そのネタ見せでの小島くんは合格しなかったんだけど、次の月には大ブレイクしていたから。
この事実は、審査した作家の見る目がないとかの問題じゃなくて、それぐらいお笑い芸人の売れる・売れないなんて誰にもわかりゃしない。
そのオーディションに関して昔から俺が言っているのは、「芸人に対してダメ出しだけはしないでくれ」ということ。その理由は、爆笑問題が若手時代にテレビ局のネタ見せに行って的外れなダメ出しをするやつらにムカついたからというのもあるけど、一番大きいのは、誰がいつ売れるかだなんてわからないと切実に思うからだ。
「嫌なことをがんばる」才能はない
審査よりも先に、とにかく自分がウケたくなっちゃうっていうね(笑)。「いまこの場で0点とか出したらどうなっちゃうんだろ?」「いやいや、さすがに『M-1』でそのボケはダメだろ」という葛藤はあるだろうけど、やっぱり0点を出してしまう気がする。いや、絶対に出す。俺にはその誘惑に勝てる自信が一切ない。
そんなわけで、才能に関しては「わからない」というのが本音だけど、その言葉と対になる「努力」もまた、微妙な言葉だ。俺は、お笑いの仕事はもちろん、小説などの文章を書くことやそれにまつわる調べ物、ある時期までしていたメモを残す行為を努力だと思ったことが一度もない。
メモに関しては小説を読むごとに感想や気に入った一節を残していたんだけど、なぜ「ある時期まで」かと言えば、いまは自分の新作を書き上げたい気持ちが強いから、ほかの人の小説を読めていなくてメモの取りようがないってだけの話。
その小説を書く時間も世間でいうところの休日にしているから、努力と呼べないこともないんだろうけど、俺の語感としては違う。好きなことをしていることのなにが努力だよって話だから。
俺の語感としての努力は「嫌なことをがんばる」となるんだけど、これがまぁ、その手の才能が子供の頃から悲しくなるぐらいに、見事にまったく一切ない。
小学校の宿題から数えてこの方、一度も努力できたためしがないから。夏休みの宿題も一切やったことがないんだけど、あえてやらないといったかっこいいものじゃなくて、毎年毎年、「初日に全部終わらせるぞ。そうすりゃあとは毎日遊べる」と思っていた。
だけど、体が動かない。次の日も「今日こそは」と思うんだけど、やっぱり体が動かない。結局、一度も机の前に座ることなく長い夏休みが終わってしまう。「こんなことがありえるのか?」と毎年毎年思いながら、それでも一度も宿題をやることなく、ダメな大人になってしまったというね(笑)。
伝統芸能が突き詰めた技術
歌舞伎や能などの日本の伝統芸能がすごいのは、「悲しい」「うれしい」といった人間の喜怒哀楽が、首の角度や手のかざし方といった所作で表現できるはずだと長い年月をかけて、技術として突き詰めたところにある。
つまり、感情表現には型があるということ。人形浄瑠璃もそうでしょ? これは、日本の芸能とそれを感じ取れる日本人のすごいところだと思うんだけど、ただの人形が泣いているように見えるのには、その型があるということだから。
もちろん、芸における型は日本の伝統芸能だけのものじゃなくて、たとえばハリウッドの名優を数多く輩出してきたアクターズ・スタジオの演技の基礎は、ソ連時代のスタニスラフスキーシステムによるところが大きい。
じゃあそのシステムがなにを伝えようとしたかというと「型は大事だよ」ということ。そういう海外の演技メソッドよりも、ずっと昔から、そのことに気づいて極めようとしてきた日本の古典芸能は本当にすごいと思う。
ただ、演技の技術も、感性という別の要素に左右されるのが、少々ややこしい。型があるのならば、誰でもそれを習得できそうなものだけど、実はそうでもないということを俺は経験したことがある。
技術を育てるベースとなる感性
それでも一度だけ、事務所の後輩がコンビを解散するかもしれないという時期だったので、彼らの漫才の演出的なことを手伝ったことがあった。
これがまぁ、無理だった。その場面ではこの型、その時はこんな感じでなどと自分なりにわかりやすく伝えたつもりでも、彼らには再現できなかった。おそらく、スポーツと同じなのだと思う。野球のバッティングで「このフォームで打ってください」と優秀なコーチが教えても、やっぱりできない人はできないし、野球感性みたいなものがすぐれた人は、すぐに打てるようになる。
では、技術を育てるベースとなる感性を才能と呼ぶのか? もしそうだとするのなら、話は最初に戻って、俺にはやっぱりよくわからない。ひとつだけ言えることがあるとすれば、もし、若い読者のなかで「俺には才能がないのかもしれない」などと悩んでいるやつがいるとしたら、そんなものは入り口でしかないということ。
たとえば、立川談志師匠。俺は間近で師匠を見ていて痛感したけど、あの人は最後まで自分の才能と向き合っていた。過去の大名人と自分を比較したり、もっと言えば古典落語そのものと格闘していた。師匠の心の内には、古典落語に勝ちたいとの願いがあったのだと思う。
だとするなら、江戸時代から明治、昭和、そして現在へと受け継がれてきた芸には到底勝てるもんじゃなくて「俺は負けた」と時には落ち込んだこともたくさんあったはずでね。あれだけの天才がそこまで悩んでいたんだから、若いやつごときが才能について悩むなんて当たり前の話で、それが入り口だし、そこからしか始められない。
「漫才が天職」とは思っていない
なかなか実現できないけど、長編映画も撮ってみたい。しかも、売れたい。でも、どうすれば売れるかなんてわからない。だからいろんなことに手を出しては失敗しているんだけど、それでも「なにかあるんじゃないか?」と探し続けている状態だから。
40歳の頃の桑田佳祐さんは、「他者との比較ではなく自分のなかで一番信じられる才能は?」との問いに「17歳の頃の感性をいまだに信じられるところ」と答えたという。
桑田さんの言葉ほどかっこよくはないけど、ふつうの大人ならいい加減自分の向き不向きとかいろいろ見えてくるはずなのに、いまだにずっとわかっていないところが俺の才能なのだろうか。いや、それも最初の田中の才能の話と同様に詭弁だと思う。
そういえば、ピコ太郎のブレイクを予見していたあの上田は俺に会うと「あんたが売れた理由がまったくわかんない」とよく口にする。その通りだと思う。そもそも、売れる・売れないがどの段階を指すのかも難しいし、やっぱり、才能や売れるというテーマは俺にはよくわからない。
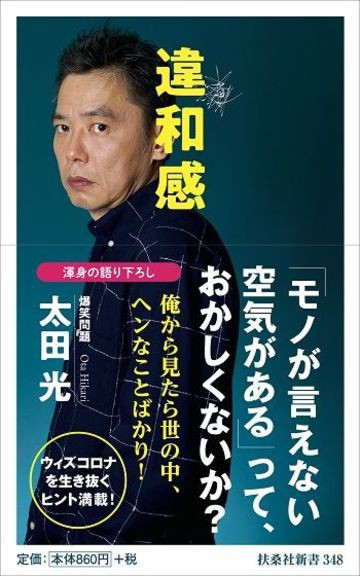
●太田 光(おおた・ひかり)
1965年5月13日埼玉県生まれ。1988年、同じ日本大学芸術学部演劇科だった田中裕二と漫才コンビ爆笑問題を結成。1993年『NHK新人演芸大賞』で、漫才では初めて大賞を受賞。同年、テレビ朝日の『GAHAHAキング爆笑王決定戦』にて10週勝ち抜き初代チャンピオンに。以降、爆笑問題のボケ担当としてテレビ・ラジオで活躍。文筆活動も活発に行っている。主な著書に『爆笑問題の日本言論』(宝島)、『カラス』(小学館)、『憲法九条を世界遺産に』(集英社新書)、『マボロシの鳥』(新潮社)、『憲法九条の「損」と「得」』(扶桑社)など。
『違和感』(扶桑社新書)本体860円+税