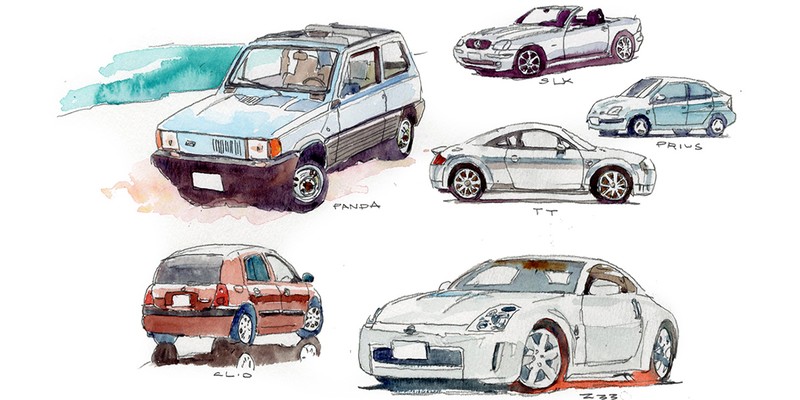2025.07.01
諦められた靴が息を吹き返す場所ハドソン靴店・村上 塁が語る継承することの意義と豊かさとは【Part.2】
全国から、修理を諦められた靴が集まる「ハドソン靴店」。リペアするとひとえにいってもその靴に刻まれてきた跡、その履き主だけの特徴は残したまま新たに命を宿していく。顧客にとって、何が大切なのかを見極める──時に大胆に、時に繊細に。靴職人、村上 塁氏は他人の靴にどう向き合うのか、倹約ではなく“贅沢”な修理のその根底をうかがったインタビュー第二弾です。
- CREDIT :
写真/トヨダリョウ 文/船寄洋之 編集/渡辺 豪(LEON)


対話から始まる、“もう一度”の歩み
村上 確かにそうですね。リペアはあくまで“現状復帰”。壊れた部分を直して、元の状態に戻すという感覚です。一方で、リビルドは“再生”。もっと踏み込んだ工程で、持ち主の思いや、靴に刻まれた時間をどう残していくかを考えながら進めます。たとえば、靴に刻まれたシワや色ムラは、人によっては“汚れ”に見えるかもしれません。でもそれって、“味”でもあり、“人生の証”でもある。「この傷は絶対に消さないでください」って言われたこともよくありますね。それが転んだ時についた傷だったり、大切な時期をともに過ごした記憶だったりするんです。

── それくらい、対話が重要だと。
村上 技術は、毎日手を動かしていれば必ず上達します。「縫うの上手いですね」って言われても、それはプロ野球選手に「素振りがうまいですね」と言っているのと同じこと。それよりも大事なのは、“その靴の先に人がいる”ということを忘れないことです。その人の人生や思い出を汲み取って、自分たちのフィルターを通して、靴を復元していく。それが僕たちの仕事だと考えています。
海を越えて、物語ごと届く──多様な靴、多様な人生
村上 よく、ありますね。たとえばこの靴は、アメリカから持ち込まれたもので、約1940年代、80年前の一足です。もともとは、お客さまのお父さまのおじさんが履いていたものですね。


なんでも、アメリカはあれだけ広い国なのに、技術的に難しい修理ができる職人がほとんどいないらしいんです。イギリスやスペインなどヨーロッパからの依頼もありますが、向こうではメーカーのラインに立つ職人が“花形”とされていて、修理の現場が必ずしも同じような環境や経験値にあるわけとは限らない。だから、全体として仕上がりの質に差が出やすいようです。
── 国によって、想像以上に違いがあるんですね……。ところで、お話を伺いながら、あちらの長靴(ちょうか)もかなり気になりました。

また、このお客さまは、「ここが当たって少し痛い」とおっしゃる一方で、「この傷は当時履いていた証だから、絶対に触らないでほしい」とも希望をいただいたので、外側には一切手を加えず、内側からカンガルー革を当てる予定です。

“味のある靴”は日々の手入れから生まれる
村上 うちは、修理をおすすめしないケースも多いんです。特にアッパー(靴の上部分)がダメになってる場合。アッパーって、メンテナンス次第で持ちが全然違うんです。車で言うと、ちゃんと洗車してワックスかけてる人と、野ざらしにしてる人の10年後の姿が違うのと同じです。

—— 修理にも“見極め”が必要だということがよくわかります。
村上 うちは見た目だけ直して、後は知らない”みたいな修理はしたくないんです。ちゃんとお客さまの将来まで考えて提案したい。そのために、うちではオールソール(靴底の全交換)をされた方に、1年間の靴磨き無料券をお渡ししています。これがあると、「半年経ってちょっとここが痛いんだけど」とか、言いやすいんですよね。そういう小さな声が拾える環境を作ることで、靴も人も、より長く良い関係が保てると思っています。

● 村上 塁
1982年、神奈川県横浜市生まれ。テレビで見たオーダー靴職人に憧れて大学を中退し、靴の専門学校に入学。その後、靴職人・佐藤正利氏や関 信義氏に師事し、靴メーカーでの実務経験も積む。2011年、佐藤氏の逝去に伴いハドソン靴店の2代目店主に。製造で培った高い技術を活かし、他店では断られるような特別な修理や難しい依頼を引き受ける。思い出の詰まった靴や形見の靴など、大切な一足を丁寧に蘇らせる技術と真摯な姿勢が評判を呼び、全国から依頼が殺到。海外から注文が届く。現在、年間1000足以上を手がける日本屈指の靴修理職人として、高い信頼を集めている。