2017.06.29
牡丹は三河、菊は信州。じつは地域ごとに名物花火がありました
一見どこにいっても同じように見える花火ですが、じつは地域によって微妙に違うって知ってました? それには花火の歴史がじつはふか〜く関係していたり、自治体の条例が関係していたり。つまり、これを知っておくと「お、さすが信州、菊がみごとだね〜」なんてさらりといえたり、「牡丹を見に愛知いこうか?」な〜んてお誘いができたりと、アクティブなオトコとしては、じつに押さえておきたい情報だったりするんです。
- CREDIT :
監修・写真/冴木 一馬(ハナビスト) 取材・文/岩佐 史絵
地域ごとに得意な花火があるって知ってました?
戦国時代が終わりのどかな江戸時代、花火が奨励されるようになりますが、火薬の扱いは徳川の親藩や雄藩にしか許されなかったために花火は特定の地域にしか根づかなかったそう。
そこでは地域性を反映した花火が発展し、現代においてもここで観るならこの花火!という得意な花火が残っているのです。

「牡丹」の本場といえば三河なのです
これが国産花火の始まりですが、三河は日本の花火を代表する「牡丹」の本場。花火づくりの“第一人者”ゆえ、もっともシンプルな「牡丹」が誕生したのも三河と考えられます。
三河が「牡丹」の元祖であるならば、三河の「牡丹」がもっとも美しいのは当然といえば当然、ですよね。

「菊」の進化を見るなら信州へ
信州で発展したのは「菊」。何重にもなった菊のバリエーションがいろいろ見られることが特徴で、地元の花火大会でも「菊」の技術を駆使した「早打ち」や「追い打ち」といった、「菊」の特性を活かした演出が多く見られます。


いまや幻になった常陸の「吊り物」
ただ、火薬をぶら下げて空中を浮遊するため現在は自治体によって禁止されており、常陸の「吊り物」はなかなか見られない幻の花火になってしまいました。


華やかに花が咲き乱れる上越の「千輪」
それゆえ、花火師さんたちはまず作りたがりません。そこを雪国の人は根性があるのでしょうか、上越の名物花火といえば「千輪」で、とにかく様々な千輪が作られています。
片貝まつりに行くと、おそらくほかに類を見ない、驚くほどに技巧を凝らした千輪花火が目白押しです。

花火の「色」の進化も見所のひとつです。
花火の基本は青・緑・黄・赤の4色。白く見えるのはアルミを燃やした銀、チタンを燃やしたら金色になり、また、基本の4色から赤と青を混ぜて紫に、と一般的には計7色がスタンダードな花火の色。
しかし90年代初頭から新たにパステルカラーの明るい色の花火が誕生し、夜空はさらにカラフルになりました。かつては真っ赤とか真っ青とか、はっきりとした基本色が出るのが理想とされていましたが、江戸時代と違いネオンサインで街が明るくなると花火が目立たなくなり、明るい色が好まれるようになってきたのです。
現在みられるのはレモンイエローやライトブルー、ジューシーなオレンジ色にゴージャスなエメラルドグリーン。
新しいカラーが登場するたび、業界を驚かせています。もちろん、製造方法はトップシークレット。“爆発物”である花火ですから、新しいものを開発するのには大きなリスクが伴います。だから誰もが気軽に作れるものではないのです。
まさに、花火の進化は命がけ。新色も新作も、そんな花火師の挑戦が生み出したものなのです。
やわらかな黄味が美しい「レモンイエロー」

開発に数年を要したという、繊細なブルー「水色」

日本でたった4社しか作れないという、「オレンジ」

花火を追って三千里 オトナな花火はこう楽しむ!
材料もさることながら、温度や湿度などさまざまな条件で微妙に色が変わってしまい、一度成功しても二度めは同じ色がでないことも。たとえばオレンジ色の花火を作れる業者は日本でたった4社しかないのだそう。
そう知るとオレンジ色の花火を見るために、その業者さんの担当する花火大会を探してみる、なんてのも、なんだかオツではありませんか。
あの花火を見るためだけにその土地へ。今年の花火は通な大人の鑑賞スタイルで行きましょうか!
● 冴木一馬
写真家。世界を股にかけ花火を撮り続けて30年。撮影だけでなく、花火の歴史や民俗文化をも調査・研究し、花火のことならなんでもござれ、花火師の資格まで有する日本唯一の“ハナビスト”。山形県出身。http://www.saekikazuma.com/
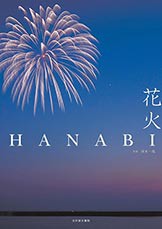
写真集『花火』光村推古書院刊
写真集『花火』光村推古書院刊
A4判 オールカラー96頁
ソフトカバー 本体2400円
ワンシャッター、多重露出をおこなわず、花火本来の姿をとらえることにこだわりぬいたハナビスト冴木一馬による花火写真集。























