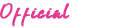2022.02.12
月9ドラマ「ミステリと言う勿れ」はNetflix的!?
Netflixのドラマは意識して操作しないと、ベルトコンベア状態でどんどん次の回がはじまり、気づいたら何時間も見る、いわゆる“ネトフリ廃人”化してしまう。各話の終わり方が次回を見たくなるようにもできているからだが、今季の月9がまさにそうだと言うのだ。
- CREDIT :
文/木俣 冬(コラムニスト)
主人公・久能整(菅田将暉)は大学生。友達も恋人もいないとはいえ彼なりに快適に暮らしている一市民・整が殺人事件の容疑者になったことをきっかけに警察関係者たちと関わり合う。至極冷静に状況と関係者たちの事情を見極めて、真相を手繰り寄せた整の抜群の洞察力に刑事たちは一目を置き捜査を頼るように。

いわゆる刑事ドラマと言う勿れ
そもそも「言う勿れ」とはミステリーじゃないのか? と言えばミステリーではある。事件のあらましを推理しているから。作家がミステリーの専門ではないという謙遜とそんじょそこらのふつうのミステリーではないという自負が混ざったタイトルなのだろう。多くの視聴者をひきつけるのは、このふつうのミステリーとも刑事ものともちょっと違う味わいである。そしてそれがこのドラマの最大の魅力である。
ちょっと違う味わいのひとつはストーリーが変則的であることだ。第1話でひとつの事件(整が容疑者になる。エピソード1)が解決した後、第2の事件(整がバスジャックに巻き込まれる。エピソード2)がおもむろにはじまった。第2の事件は翌週の第2話へと続き、さらに第3話にも続いた。

いったい私は何を見せられているのかと思うほどにガロ中心のエピソードはムードが違っていた。主人公・整はどこ行った? いきなり主人公交代? それはネットでも話題になっていた。だがそれは整が第1話で言うところの、真実は人の数だけあり「違う視点」で見ると印象がずいぶんと違うことが浮かび上がってくるもので、それをセリフだけではなく別の登場人物の視点によって実践して見せるという真摯な姿勢とも言えるだろう。
そんなふうに好意的に捉えたとはいえさすがに斬新ではあったが、永山瑛太には華がありひき込まれてしまう。しかも永山瑛太が一瞬彼とはわからないビジュアルをしていたことにも挑戦的なものを感じた。
毎回欠かさず見なければ振り落とされる?
ところが第4話(エピソード3)では何事もなかったように整のターンに戻る。今度は爆弾魔(柄本佑)と整の攻防。ガロと何か深い関係性を感じさせた整だったが柄本佑演じる犯人とも心を通わせていく。あれ? ガロは? 整は恋人も友人もいないことが本当は寂しくてわかりあえる人を求めているのだろうか。もしかしてこれは整の心の旅?
霧のように先がぼんやりとして掴み所がないながら、すでに第3話の終盤、柄本佑以降、続々登場するゲストキャラクターが紹介されていて、これからは毎回1話完結させながら、ガロとの再会譚に向かっていくのだろうなあとなんとなく想像はできる。なかなか手のこんだ構成だが、これは原作を踏襲している。優れた原作をヘタにいじらずできるだけ寄せてドラマ化する。それは大変賢明なやり方である。
本来、連続ドラマは1話完結ものが好まれるとされる。1話完結ものは、誰もがいつでも入ってこられると同時に、誰もがいつでも抜けることも可能である。それだと世帯視聴率が稼げたとしても番組の熱狂的なファンがつかない。その点『ミステリ』は後者の可能性をもっている。これはNetflix的と言っていいかもしれない。
Netflixのドラマは各話の終わり、エンドクレジットを意識的に「見る」にしないとそのまま次の話がはじまってしまう。そのためベルトコンベア状態でどんどん次の回を見てしまうのだ。というシステム的なこともあるし、各話の終わり方が次回を見たくなるようにもできている。続きが気になる感情と流れるように次回につなぐシステムが絶妙で、気づいたら何時間も見て、いわゆる“ネトフリ廃人”化してしまう。
「1話完結もの好き」も「連続もの好き」も満足
『ミステリ』は1話完結ものが好きな人も、凝った連続ものが好きな人、その両者を満足させることができる。最初に、物語の終盤——整とガロとの決着があると宣言してあるので、それを期待できる。それまではすべてが1話完結とはいかなくても個々のエピソードを楽しむこともできる。第4話は1話完結ものの形式で、かつ、原作にもあった坂元裕二のヒットドラマ『カルテット』のセリフを引用した会話を使用して、原作ファンも『カルテット』ファンもSNSで盛り上がっていた。
事件のあらまし(推理)は整が長セリフで説明してくれるのでポイントはつかみやすい。状況説明と整なりの持論をとうとうと語ることがうっとおしいとか気持ち悪いとか思う人もいるようだが、そこは菅田将暉がほどよく人間味があってとっつきやすく演じて緩和している。
社会をちくりと皮肉るものが好きな視聴者も一定数いて満足できるものにもなっている。美術や照明など画が凝っていて、クラシックの劇伴がここぞというところを盛り上げる。取り調べ室での会話劇の緊張感から猟奇的な犯罪のスケッチまで刑事もののあらゆる要素が満載。刑事ものあるあるの指摘——「真実はひとつなんてそんなドラマでしか言わないセリフをほんとうに言う人がいるなんて」「真実はひとの数だけあるんですよ」「でも事実はひとつです」(第1話より)もある。
それこそいろんな視点でミステリ(刑事もの)を楽しめる工夫が凝らされている。じつによくできた話なのである。チーフ演出家の松山博昭は編集に定評のある人物なのでドラマチックにカットを重ねて盛り上げて見せる。
余裕を持った制作環境も奏功
通常の連ドラのスケジュールだと放送直前まで撮っているようなことも少なくなく、次回予告の素材すら足りないことがあるくらいだ。その分、視聴者の反響で内容が変更することもあるとはいえ、後半どうしても粗が目立ってくる。『ミステリ』は原作があってその行き着く先が見えている。その安心感はクオリティーの高さにも繋がっている。
しかもコロナの感染対策で撮影がしづらい今、俳優の芝居のうまさにかけるしかないところもある。場数を踏んだベテランや才能ある若手の会話劇で説得力あるものにするしかなく、『ミステリ』はそれに足る内容でもあった。期せずしてかしてないのか定かではないが、『ミステリと言う勿れ』がとにかくちゃんと続けて見ることに意義のあるドラマになったことは喜ばしい。