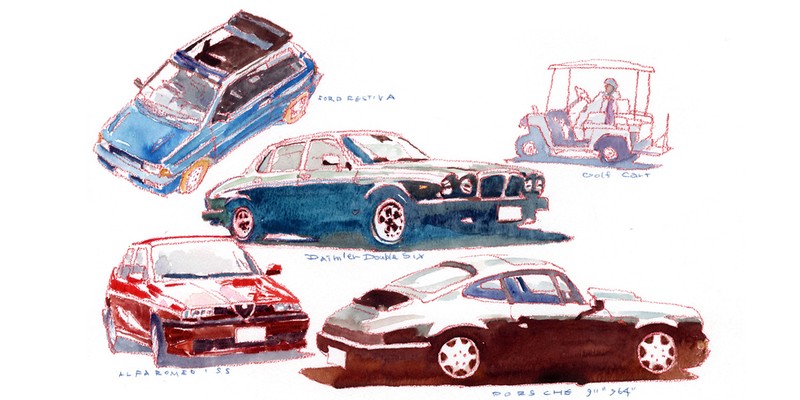人間、歳をとると「和」の世界に親しみを覚えるのは何故でしょう? 編集部で一番涅槃に近いせいか、最近とみに「和モノ」が気になる今日この頃です。

先日は東京国立近代美術館で行われている樂焼の展覧会「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」に行ってきました。恥ずかしながら茶の湯の茶碗である樂茶碗を初めてじっくりと見たのですが、これが本当に素晴らしい! 心を鷲掴みされるような感動を覚えましたのでご紹介を。
初代長次郎は千利休の求めに応じて侘茶にふさわしい茶碗として樂茶碗を作りました。代表的なものは「黒樂」と言って一面真っ黒で何の飾りもない無骨な形をしています。当時の桃山文化は豪壮・華麗で煌びやかな表現が人気でしたが、その中で、あえて黒一色を纏うことで「無作為の美」という思想性を表現する「黒樂」は、まさに時代に挑戦する茶碗だったのです。
というのは後から得た知識で、最初はほとんど何も知らぬまま初代長次郎の作品に接したのですが、それでも黒樂茶碗を目にした瞬間、圧倒されるものがありました。全体の絶妙なバランスと細部の完璧な美しさは揺るぎない「静」の佇まいを見せるのですが、一方で茶碗からは底知れぬ「動」のエネルギーが発散しています。その相反する相貌が、手のひらにすっぽりと収まる小さな茶碗の中に瞬時に立ち現れるさまは、まさに展覧会のタイトル「茶碗の中の宇宙」という言葉を彷彿させるものでした。
その後、機会があって当代である十五代樂吉左衞門さんのお話を伺いました。樂焼は、また「今焼」とも呼ばれ、伝統を重んじながらも先代の技を継承するだけでなく、常にその時代と向き合った自分だけの「今」の碗を作り続けなければならないそうです。その意味で樂焼の歴史は不連続の連続なのです。

右●十五代 吉左衞門 焼貫黒樂茶碗 平成24年(2012)東京国立近代美術館蔵
ちなみに私が展覧会を訪れた時には、意外にも若い(それも美しい!)女性客が多く、皆、食い入るように茶碗を見ているのが印象的でした。最近の若い女性はオヤジ達よりよほど好奇心旺盛のようです。「茶碗の中の宇宙、一緒にのぞきに行かない?」なんて誘い文句でどうぞ彼女を春の美術館へ連れ出してくださいませ。

茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術
開催概要
会期/開催中。5月21日(日)まで。
会場/東京国立近代美術館
公式HP/http://raku2016-17.jp