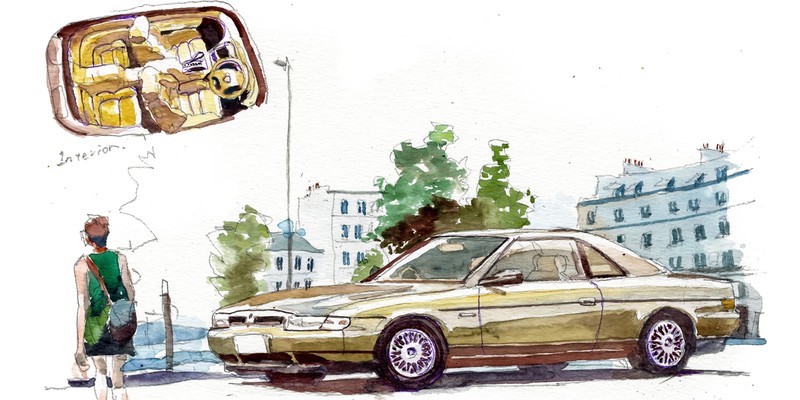2017.03.15
開きたくなるドアとは──
クルマとのファースト・コンタクト――それは、視覚的な面を別にすれば最初に手を触れる「ドアハンドル」。それだけに各自動車メーカーは実はドアハンドルを念入りにデザインしているのだが歴史的な変遷を振り返ると、地域や時代に応じた多種多様なトレンドが!
実はクルマの安全性とも密接につながっていた!
グリップタイプと違ってボディから無骨に飛び出していないことから当時、フラップ式は“スタイリッシュなドアハンドル・デザイン”として好評を博し、アメリカや日本でまたたく間に広がっていった。
また、ボディの面作りがフラットになるため空気抵抗を抑えるうえでも有利と考えられていたようだ。

ドアのオープニングは後ろにいくに従って微妙に上昇させることで軽快感を演出するとともに、真横から見た時に女性のひざ下が美しく見えるよう計算された。ディテールへのこだわりにもヌカリない。
なぜだろう? その理由は「フラップ式は安全ではない」との認識が広まってしまったからだ。
意外かもしれないが、ドアハンドルはクルマの安全性に大きく関わるパーツでもある。
というのも万一クラッシュしてボディが変形した場合、ドアを開くには通常とはケタ違いに大きな力が必要となるが、フラップ式ではドアに大きな力をかけることが難しく、このため救助作業が困難になると考えられたのだ。
この点、グリップタイプであれば手で引くだけでなく工具を使うこともできるので、より迅速にドアを開き乗員を救助できる可能性が高い。つまり、安全性でいえばグリップタイプが優位なのだ。
MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC [メルセデス・ベンツ GLC 250 4マチック]

Cクラスをベースに誕生したメルセデスSUVの最新作がGLC。余裕あるロードクリアランスと4WDシステムで本格的なオフロード走行が可能なほか最新の2.0ℓ直噴ターボ+9速ATの効率のいい走りも楽しめる。
全長×全幅×全高:4660×1890×1645㎜ ホイールベース:2875㎜ 車重:1800㎏ エンジン:直4 2.0ℓ ターボ 最高出力:211㎰ 最大トルク:350Nm 価格:628万円(税込)/メルセデス(メルセデス・コール)
同社はことさら頑丈そうなドアハンドルを採用しているが、これはクルマの安全性を視覚的に訴える効果があるほか、エッジを丸めた優しいデザインゆえに女性のネイルを傷つけないともいわれる。
安全性が優しさにも結びつくことを示すクルマの、典型的な例といえるだろう。

メルセデス伝統のグリップ式ドアハンドル。堅牢な作りで万一の事故の際も安心なほかネイルをした女性の手にも優しい丸みを帯びたデザインが特徴だ。

ドア内側に設けられたシート調整スイッチ
ドア内側に設けられたシート調整スイッチ
シートの形状をそのまま模したシート調整スイッチをドアの内張に設けるのもメルセデスの伝統。見やすくまた直観的な操作が可能という特徴をもつ。
何とかしてスタイリングと安全性を両立したドアハンドルを作れないだろうか──?
デザイナーたちのそんな欲張りな要望から誕生したのが現在、ラグジュアリー・スポーツカーメーカーの間でもてはやされているリトラクタブル式である。
Aston Martin RapidE S [アストンマーティン ラピードS]

スタイリングやパフォーマンスはほかのアストンマーティンと同等のレベルにありながら、4枚のドアとフル4シーターのスペースを備えた稀少なモデルがラピードS。“S”にモデルチェンジして格段に洗練された。
全長×全幅×全高:5019×2140×1360㎜ ホイールベース:2989㎜ 車重:1990㎏ エンジン:V12 6.0ℓ
最高出力:560㎰ 最大トルク:620Nm 価格:2503万4983円(税込)/アストンマーティン(アストンマーティン・ジャパン)
肝心の安全性については、しっかり握れるバーが飛び出してくるので、フラップ式に比べれば確実に力を込められるほか、車種によってはヒンジ部分に火薬が内蔵されていて、事故が起きたと判断される場合にはこの火薬でヒンジを破壊し、容易にドアを開閉できるようにしたものもある。

リトラクタブル式のドアハンドルは微妙な曲線を描いていて手にぴったりとフィットする形状。まるで人と握手しているかのような感覚が味わえる。
古くは1994年発表のTVRサーブラウ、新しいところではマクラーレンの各モデルがそうで、小さな電気スイッチを押すとロックが解除され、例えばマクラーレンであればそのままドアを引き上げて車内に乗り込む形式となっている。
翼を広げた鳥から連想して名付けられたドア
ガルウィングといえば、1950年代にデビューしたメルセデス・ベンツのスポーツカー300SLが元祖とされる。その300SLは、軽量かつ高剛性のボディを実現するために、サイドシルと呼ばれる、いわゆるドアの敷居部分が厚くかつ極端に高く、しかもスポーツカーゆえにルーフが相対的に低いため、乗り降りが著しく困難になることが予想された。
そこでルーフ部分までが一体となって上方に跳ね上がるドア、ガルウィングが考え出されたのだ。これであればルーフの切り欠き部分からカラダを下向きに落とすようにして腰掛けられるため、高いサイドシルでも乗降の邪魔にならないという発想だった。
そして、ドアを開けた状態を前方から見ると、ちょうど翼を広げたカモメ(Gull=ガル)を連想させる姿となるため、ガルウィングと名付けられることに。
Tesla Model X [テスラ モデルX]

モデルXはテスラにとって初のSUVだが、優れた環境性能に加えて航続距離は542㎞に達するなど、テスラらしさを満載。駆動系は4WDで7人乗り。フロントドアは左右に開き、リヤドアのみファルコンウィングとなる。全長×全幅×全高:5037×2070×1680㎜ 車重:2468㎏ モーター:193kw+375kw 価格:895万円〜(税込)/テスラ(テスラモーターズジャパン)
同社はこれをファルコンウィング(ハヤブサの翼)ドアと名付けているが、通常のドアに相当する範囲からルーフの切り欠きにいたるまでの部分が、ルーフに取り付けられたヒンジを軸に左右30㎝の幅さえあれば、まるで鳥が翼を広げるように開くため乗り降りが容易なほか、例えばチャイルドシートを取り付けるのも便利と主張している。
このガルウィング式ドアにはいくつかの分家ともいえる存在がある。その代表的なものがランボルギーニ カウンタックなどに見られるシザーズドア、もしくはジャックナイフドアと呼ばれるタイプ。
これはヒンジがドア前方に位置していて、しかもヒンジの回転軸がクルマの全幅方向に設けられたドアである。クルマを真横から見ると、ドアがヒンジの回転軸を支点として前方に大きく回転するようにして開く様がハサミ(シザーズ)もしくはジャックナイフのように見えるところから、この名が付いたらしい。
その目的とするところはガルウィングと同じで、低いボディへの乗降性を良くすること。また、ガルウィングと異なり、ドア開閉の際に車体の左右に大きなスペースを必要としないので、天井さえ高ければ幅方向にあまり余裕がない場所でも乗降が可能というメリットがある。
ところで、カウンタックは全高が極端に低いこともあって後方視界が悪く、バックする時は車外からの誘導が必要不可欠とされていた。
そこでカウンタック・マニアたちが編み出したのがカウンタック・リバースという技。これはバックする前にまずドアを開け、上半身を捻るようにしてサイドシルに腰掛けて後方を確認しながら、ステアリングやペダルを操作してクルマを後退させるテクニックで、これがスムーズにできると本物のカウンタック乗りと見なされることもあるようだ。
F1で開発されたドアが実用化されるまで
ボディが開いている状態を真横から見るとシザーズドアと変わらないが、ディヘドラルドアは開く過程でボディの外側にドアが移動する形となるため、乗り降りの際のスペースがより大きくとれるというメリットがある。
Mclaren 540C [マクラーレン 540C]

日常性を重視したマクラーレン・スポーツシリーズのなかでもっともコストパフォーマンスが優れているのがこの540C。2200万円を切る価格でマクラーレンらしいパフォーマンスとクオリティをすべて味わえる。
全長×全幅×全高:4530×2095×1202㎜ 車重:1350㎏ エンジン:V8 3.8ℓターボ 価格:2188万円(税込)/マクラーレン(マクラーレン東京)
ディヘドラルドアは、レーシングカーデザイナーの鬼才であるゴードン・マーレイが手がけたマクラーレンF1で初お目見えして以来、すべてのマクラーレン・ロードカーに採用されている。
マーレイは早くからディヘドラルドアの有用性に着目していたが、実用化に当たってはドアを開閉する際の動きを詳細に検討。
ドアが開いた状態でも手が届きやすいか、開け閉めする際に必要な力は重すぎないかなどにも細心の気を遣いながら開発を進めていったという。この優れた伝統は、最新のマクラーレンにもしっかりと息づいている。
BMW i8 [ビー・エム・ダブリュー i8]

地球環境を守るため、CO2排出量削減を最優先して開発されたスーパースポーツカーがBMW i8。カーボンモノコックやプラグイン・ハイブリッドを搭載、直3 1.5ℓエンジンで最高速度250㎞/hに到達する超高効率を誇る。
全長×全幅×全高:4690×1940×1300㎜ 車重:1510㎏ エンジン:直3 1.5ℓターボ 価格:1991万円(税抜)/BMW(BMW i カスタマー・インタラクション・センター)
「駐車した時は降りられたけど、戻ってみたら隣のクルマの駐車位置が近すぎて乗り込めなかった」なんていうケースもあるようだから注意も必要だ。
さて、クルマのドアには事故の際に乗員を保護し救出する出口という安全上の大切な役割もあるが、もうひとつ忘れてはならないのが文字どおりクルマのキャビンへの入口となっている点にある。
いうまでもなくクルマの中は、移動するために密閉される、ある種の異空間。例外を除くと、一度乗り込めば目的地まで開かれることのない言わば“どこでもドア”だ。そんなクルマのドアを開けることは、その異空間に飛び込む通過儀礼なのだから、そこに何らかの演出が施されていたとしても不思議ではなかろう。
ましてや非日常を味わうために生まれてきたようなスーパーカーであればあるほど、ドアそのものやドアを開けるという行為に、もっと祝祭的な意味が込められていてもいいのではないだろうか。
車内と外界を隔てるうえで重要な意味を有しているドアと、そのドアを開けるためのドアハンドルの世界は、紐解けばかくも奥深いのだ──。